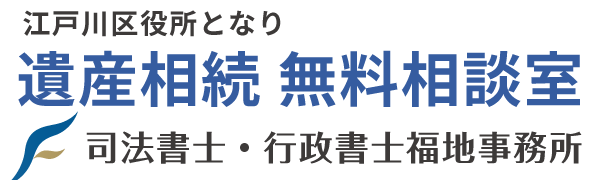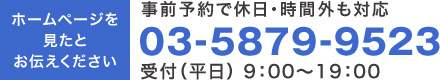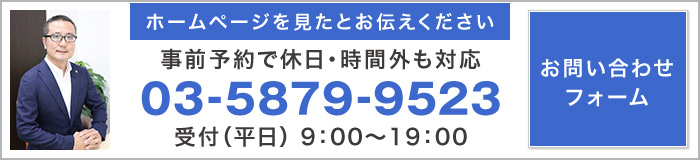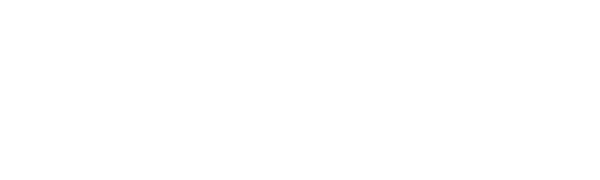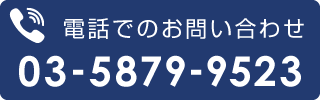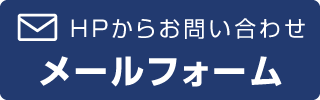本日、令和2年4月1日に民法の改正法が施行されました。
120年ぶりの大改正とも言われています。
相続法も債権法も大きく変わっていますが、相続法では、配偶者居住権の新設が一番大きな変更です。
配偶者居住権の詳細については以前割と細かく書いていますのでそちらを参考にして下さい。
ここでは、配偶者居住権が有効になる日付について書きたいと思います。
まず、配偶者が亡くなった日付 令和2年4月1日以降
これはある意味、施行日以降なので当然かと思います。
では、令和2年4月1日より前に作成した遺言書等では配偶者居住権は効力がないのでしょうか?
結論としては、遺言書作成日、遺産分割した日、いずれも令和2年4月1日以降でなくてはなりません。
もう1つ大事なことがあります。
配偶者居住権は登記をしないと第三者に対抗できません。
わかりやすく説明します。
ご主人が亡くなって、奥さまと長男の2人のみが相続人の場合で考えてみて下さい。
自宅を長男が相続し、奥さまが配偶者居住権を取得しました。
奥さまは長年、ご主人と暮らしてきた自宅を名義こそ長男に譲ったけれども、配偶者居住権があるのでずっと住み続けられるはずでした。
そういう制度なのですから。
しかし、奥さまは配偶者居住権を登記することを忘れていました。
そうこうしているうちに、長男がお金に困って第三者に自宅を売ってしまいました。
そして、その第三者は所有権の登記を取得してしまいました。
でも、配偶者居住権があるのだからずっと住み続けられるのでは?
と考えるかもしれません。
しかし、このケースでは原則、奥さまは自宅を購入した第三者に請求されたら自宅を出て行かなくてはなりません。
なぜでしょうか?
それは登記をしていなかったからです。
登記には権利を第三者に主張することができるという効力があります。
奥さまは登記を怠ってしまったので、新しく購入した第三者に主張できないのです。
せっかく遺言書や遺産分割で配偶者居住権を定めても登記をしないと権利を失うかもしれません。
司法書士は登記の専門家です。
配偶者居住権を含む相続の相談もお待ちしております。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。