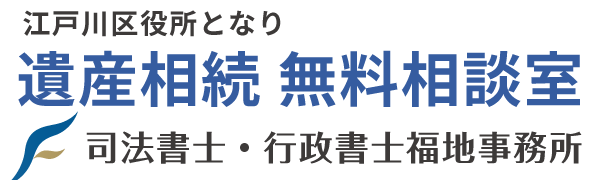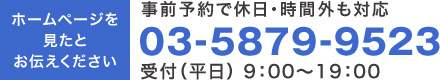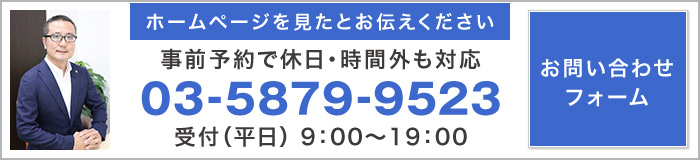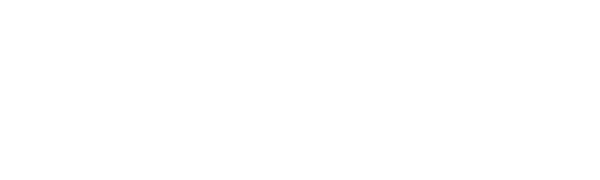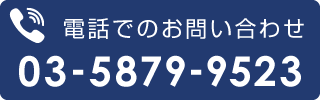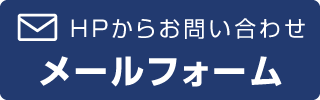今回は意外と相談の多い遺言書に押す印鑑についてクイズ形式(?)で書いてみたいと思います。
第1問
自筆証書遺言書の印鑑は実印じゃなくてはダメ?それとも認印でもいい?
答えは、認印でもOKです。
これは、民法968条に「…印を押さなければならない。」と記述があるだけで、実印とは書いてないので、認印でも有効です。
ただし、私の事務所で相談された方にはできれば実印で押印して下さいとお話しております。
その理由はいざ裁判になった時に、実印を押してあることで、その自筆証書遺言書が本人が書いたことの証拠力が上がるからです。
もちろん、実印が押してあれば絶対かというとそんなこともないのですけど、実印の方が望ましいです。
ちなみに公正証書遺言を作成するときは必ず実印です。
それは公証役場で作成する場合には本人確認の意味も含めて実印での押印と印鑑証明書の提出が必須だからです。
第2問
認印でいいのなら、拇印(指を朱肉につけて指紋を押したもの)でもいいの?
答えはOKです。
これには最高裁の判例はあります。(最判平成元年2月16日)
認印でも問題ないのに、拇印でダメってのは無理があるかなっていうことと、日本の文化として拇印というのものが存在しているので認めても問題ないでしょうというところです。
第3問
拇印でいいのなら、花押でもいいの?
ちょっと花押と言ってもピンとこない方が多数だと思うので簡単に花押を説明します。
花押とは、昔の戦国大名や総理大臣などがするサインで、そのサインにより本人が書いた文章だと証明するものに使っていたものです。
それを踏まえてどう思いますか?
答えはNGでした。
これにも最高裁の判例があります。(最判平成28年6月3日)
理由は、やはり花押というものが一般的ではないからということです。
それとあくまでサインであって印鑑ではないということもあります。
そうはいってもこの判例の当事者は由緒正しい家の方だったようですし、そういうケースではいいのではと思うところもありますが、最高裁は否定しています。
第4問
外国人が日本に帰化した場合でサインのみで印鑑を押さなかった場合は大丈夫か?
答えはOKです。
ちょっと古い判例ですが最高裁が示しています。(最判昭和49年12月24日)
元ロシアの方なのですが、ヨーロッパでは押印の風習がなく、帰化したあとも官庁に出すような書類にしか押印していなかったからというのが理由のようです。
もちろん、押印する方が無難ですので、帰化されている方も押印はして下さい。
第5問
遺言書が2枚以上になってしまったときに契印(紙と紙を印鑑を押して繋ぐこと)をしないで署名がある紙にしか押印がない場合は大丈夫か?
答えはOKです。
ただし、判決文(最判昭和36年6月22日)には
「遺言書が数葉にわたるときであっても,その数葉が一通の遺言として作成されたものであることが確認されればその一部に日付,署名,捺印が適法になされている限り,右遺言書を有効と認めて差支えないと解するを相当とする。」
とあるので、必ずしもOKではなさそうです。
そりゃそうですよね。
勝手に第三者が自分に有利な文章を1枚加えても有効じゃ困りますものね。
文章全体を判断して1枚の遺言書として確認できればということなので、遺言書が2枚以上になってしまう場合には必ず契印を押した方が良いです。
どうでしたか?
クイズ形式というか、司法書士や行政書士の試験問題みたいだったかもしれませんね。
主に判例のあるものを中心に例示してみましたが、判例はその事件の場合で判断しています。
同じようなケースでも事情や時代背景が変われば判例が変更されることもありえます。
せっかく遺言書を作成するなら、後々に争いがおこならいように形式に乗っ取って作成した方が良いでしょう。
遺言書作成のご依頼ご相談お待ちしております。
江戸川区で遺言・相続手続き、相続放棄は司法書士福地事務所 代表 福地良章

はじめまして。司法書士の福地です。
1973年、千葉県市川市の公園や空き地が遊び場だった住宅街で育ちました。毎日走り回っていた子供時代を過ごしました。
大学卒業後、就職氷河期に食品機械メーカーの営業職を経験。お客様と深く関わりたいという想いから、接客業である飲食店の店員に転職し、大きなやりがいを感じていました。その後、「相続」という出来事が私の人生を大きく変えることに。祖母の相続で親族間が揉め、裁判にまで発展した苦い経験から、「当たり前の日常が、相続で壊れてしまうようなことは起きてほしくほしくない」という強い想いを抱き、司法書士を目指すことを決意しました。千葉司法書士会の会長を務められた先生のもとで14年半修行し、特に500件以上の相続案件に携わらせていただきました。この経験から、「やはりお客様の声を直接伺い、寄り添って仕事をするのが私の天職だ」と確信。2019年(令和元年)に独立・開業しました。家族(妻、長男9歳、次男4歳)とのパン・スイーツの食べ歩きが何よりの楽しみです。東京東側や千葉エリアの隠れた名店を探すのが得意です。「あの時の私のような思いをする人を減らしたい」という強い原体験を胸に、お客様の想いを汲み取ったサポートをお約束します。